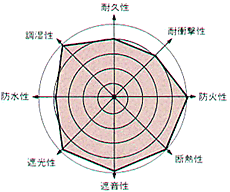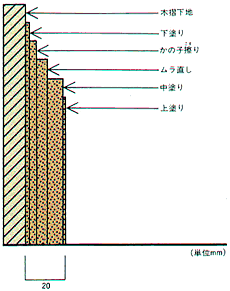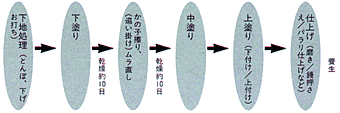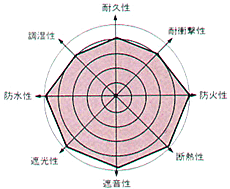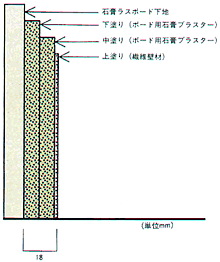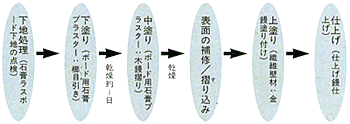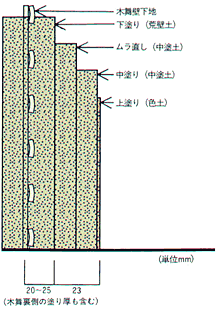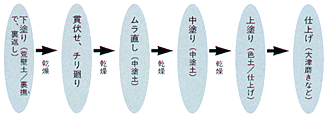TOPICS
2010年5月12日
漆喰塗のテクスチュア
仕上げの程度にかかわらず得られる、表情の豊かさが魅力
| 漆喰(しっくい)仕上げは、長い歴史の中で培われ洗練されてきた左官工法である。ごく簡易な仕上げから丹精込めた上等な仕上げまで、それぞれに価値ある表情がある。「撫で」「押さえ」「磨き」などの鏝操作により、独自の質感を備えた幅広いテクスチュアを創り上げることができる。 |
| 漆喰押さえ仕上げ |
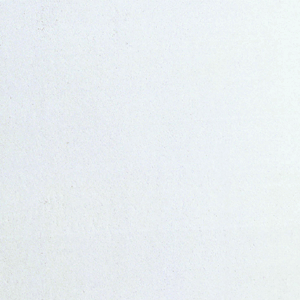 |
| 歩掛 3m2/人日 特徴 最も基本的な漆喰仕上げの一つ。これまで土蔵の壁などに多く行われてきたもので、金鏝などで押さえて仕上げる。 |
| 漆喰パラリ仕上げ | 土佐漆喰押さえ仕上げ | 漆喰引摺り仕上げ | ||
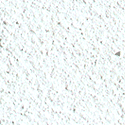 |
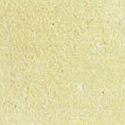 |
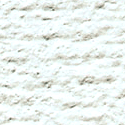 |
||
| 歩掛 3m2/人日 特徴 漆喰を撫でる程度で粗面に仕上げるもの。京都御所の壁にもこの仕上げが用いられている。粗放な表情が味わい深い。 |
歩掛 3m2/人日 特徴 土佐漆喰は一般の漆喰と異なり、糊を混入しないため水に強く、厚塗りができる。また施工後は、白色に変化していく。 |
歩掛 3m2/人日 特徴 引摺ることで表面に微妙な凹凸を加味する。漆喰の持つ柔らかな質感に、さらに深みを与える仕上げ。 |
| 卵漆喰押さえ仕上げ | 黒漆喰本磨き仕上げ | 赤漆喰押さえ仕上げ | ||
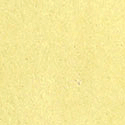 |
 |
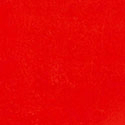 |
||
| 歩掛 3m2/人日 特徴 一般に「白壁」のイメージが強い漆喰だが、色粉を加えることで、一味違った表情を創り出すことができる。 |
歩掛 2m2/人日 特徴 灰墨を入れた漆喰をムラなく塗り付け、丹念に磨き上げていく。その微妙な光沢は落ち着きと格調高さを感じさせる。 |
歩掛 2m2/人日 特徴 赤い顔料を加えた漆喰を塗り付け、平らに押さえて仕上げる。鮮やかな発色の中にも不思議な趣きがある。 |
|
湿気の呼吸性や断熱性に優れ、種類も豊富 |
| ■特色 |
| 漆喰は、消石灰に砂、糊、スサなどを混入した日本独自の塗り壁仕上げ材料。城郭や土蔵など伝統的建物に塗られた純白の漆喰壁が広く知られるが、色粉を加えた色漆喰や材料に糊を使わない土佐漆喰など、その種類は実に豊富である。最近は材料が入手しづらくなっているが、自然のサイクルに適合した塗り壁として、その価値が再び見直されてきた。 |
| ■適した部位 |
| 材料の調合によって可塑性が自由に調整できるため、住宅・一般建築の内外壁、塀などにとどまらず、屋根のほか彫塑材としても使われる。 |
| ■性能評価 |
| 古くから土蔵など気密性の高い建物に多く使われてきたように、湿気の呼吸性や断熱性に優れている。また、その防火性能についても相当高い評価が与えられる。 |
|
| ■施工工程 |
| 強度が低いため、塗り厚を薄くし、塗り回数を多くするのがポイント。木摺下地の場合、とんぼの一つを延ばして下塗りし、木摺間に十分に摺込む。下塗り後は10日以上おいてムラ直しを行った後、残りのとんぼを摺り込んでいく。上塗りは中塗りが乾ききっていない状態を確認して行う。これより前工程ではできる限り通風をなくすのが良いが、上塗り後は逆に通風を与えて乾燥させるようにする。低温下での施工は避ける。 |
|
|
| ■下地 |
| 木摺や木舞壁、土真壁などの伝統的な下地のほか、コンクリート系、レンガ、セメントモルタルにも適合する。また、剛性はこれらにやや劣るが、鋼製金網やラスシート下地も使用できる。石膏ラスボード下地には、その表面にアルカリ侵入を防ぐサイジング処理を十分に施して使用する。 |
| ■材料と調合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
糊材には、ぎんなんや、つのまた(角又)などの海藻糊(ふのり)のほか、種々の化学糊が用いられ、これらを消石灰や貝灰と調合して使用するが、現在は既調合の袋詰め材料を用いることが多い。スサには麻系統の材料が多く使用され、漆喰の収縮性を低減するために川砂を混和することもある。なお、土佐漆喰には糊材は使用しない。
|
| ■仕上げ |
| 【磨き仕上げ】麻スサを数層にわたって塗り付けた上に、さらに紙スサを数度にわたって塗り付け、最後に押さえ込んで、磨き鏝や手擦りで丹念に磨き上げる。相当な日数を要する最上級の仕上げ。 【鏝押さえ仕上げ】磨き仕上げより塗り付ける層の回数を少なくし、最上層は磨かずに鏝で固く押さえ込んで仕上げる。表面の質は鏝のかけ具合によって微妙に変わってくる。 【色もの漆喰仕上げ】中塗りが終わり、約1日放置した後、水引き加減を見て色もの漆喰を薄く塗り付けていく。その後、数層にわたって色もの漆喰をムラなく塗り付け、最後に撫で鏝で通し撫でを行って丁寧に仕上げる。冬場の色もの仕上げはムラが出やすいので避ける。 |
| ■メンテナンス |
| 漆喰に混入する糊は保水性を高め、作業性を向上させる利点を持つが、その半面、乾燥後の収縮率が高いため、時としてクラックが入ることがある。その防止のためにはスサを塗り材に混入するとともに、塗り厚をできるだけ薄くし、塗り回数も多くする。 |
 |
 |
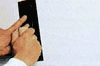 |
 |
| かの子擦りの施工 | 上塗り(塗り付け)の施工 | 上塗り(押さえ)の施工 | 引摺り仕上げの作業 |
2010年5月12日
繊維塗壁のテクスチュア
和風・洋風を問わない適応性があり、バリエーションも豊富
| 繊維壁材はその種類・品質ともに製品のバリエーションが豊富で、和風・洋風を問わない幅広いテクスチュアを創り上げることができる。施工にも比較的手間がかからず、コストメリットもあることから、内装仕上げ材としての実用的な性能は相当高いといえるだろう。 |
| 土壁風仕上げA(聚楽風) |
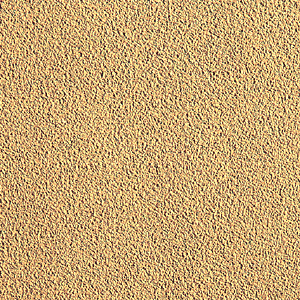 |
| 歩掛 4~5m2/人日 特徴 聚楽土の落ち着いた色合いとたたずまいを、高品質に再現したテクスチュア。 |
| 土壁風仕上げB(錆聚楽風) | 土壁風仕上げC(藁聚楽風) | 綿壁風仕上げ | ||
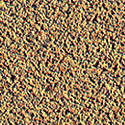 |
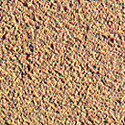 |
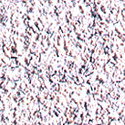 |
||
| 歩掛 5m2/人日 特徴 土壁の錆入り仕上げを表現。天然素材の持つ豊かな質感と味わいを、短い工期で提供することができる。 |
歩掛 5m2/人日 特徴 藁スサという天然素材のテクスチュアを用いた、素朴さと落ち着いた表情が魅力。 |
歩掛 5m2/人日 特徴 綿の柔らかな風合いと温もりを表情豊かに提供する仕上がり。かつて和室の内装仕上げに流行した。 |
| 砂壁風仕上げ | ||||
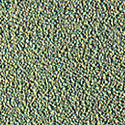 |
||||
| 歩掛 4m2/人日 特徴 砂壁の落ち着いた色合いとテクスチュアを活かした仕上がり。 |
|
多彩なテクスチュアが表現できる、内壁仕上げの代表格 |
| ■特色 |
| 塗りやすく作業性の高さを備えているという利点から、1950年代より内装仕上げとして急速に普及した。鏝ムラが出にくく、高度な熟練技能を要しないことも、多くの左官技能工に親しまれてきた要因の一つ。繊維壁材は各メーカーより数多く市販されており、和・洋室いずれにも適用する品質とバリエーションが確保されている。そのため多彩な表現が可能である。 |
| ■適した部位 |
| 主に内壁や天井に用いられる。ほとんどが人目にさらされる部位であるだけに、壁材メーカーも各種テクスチュアの開発に力を注いでいる。 |
| ■性能評価 |
| 塗面にびひ割れが起きにくく、内装には十分な耐久性を持つ。現在も調湿機能・防カビ・環境汚染対策などの向上を目指し、新製品が次々と開発されている。 |
|
| ■施工工程 |
| 施工は下地が乾燥した後で行い、上塗りではなるべく薄く塗り付ける。厚いと乾燥が遅れるうえ、乾燥後チリぎわが反曲する原因となる。また、塗り材に含まれる繊維が長い場合は、乾燥後に下地が見えてしまうことがあるため、心持ち塗り厚を厚くとるようにする。同様のことは、白系など淡い色目の塗り材を使用する場合にもいえる。ただし必要以上の厚塗りは、剥落の原因になるので避けなければならない。 |
|
|
| ■下地 |
| 一般的には左官工事の中塗り面を下地とする場合が多い。ALCパネルやPCパネルなどの合板系下地や、ボード系下地、コンクリート下地が使われるケースも少なくない。また、セメントモルタル下地やドロマイトプラスター下地はアルカリ性が高いため、下地処理を施すか、耐アルカリ性の壁材を使用する。このほか土壁・漆喰壁・石膏プラスターなどの既成の下地にも幅広く適応している。 |
| ■材料と調合 |
| 市販品はそのほとんどが、3.3m2塗る分量の壁材を1袋分として詰められているため、現場ではこの量を目安に指定量の水を加えてよく混和する。材料によって異なる場合もあるが、混和した後、糊材を繊維質に十分浸透させるために半時間程度放置しておく。 |
| ■仕上げ |
| 塗り付けていく途中で、材料の中の繊維質が固形化する場合がある。この様な場合は作業を中止し、その固まりを必ずきれいに取り除くようにする。上塗り塗り付け後は、水引き加減を見て仕上げ鏝を使って丁寧に鏝ムラを取っていく。仕上げ時の「返し鏝」は避ける。また、寒冷下での施工は見合わせるか、暖房をして5度以上の室温を確保する。施工後は通風を良くして、乾燥を速めるように心がける。 |
| ■メンテナンス |
| 塗面の状態によっては、施工後5~6年を経て表面の塗り材が次第に剥落してくることがある。原因としては必要以上の厚塗り、糊材の劣化などが考えられるが、その対応策として塗り材にボンドを混入しておくと良い。また、カビや藻の発生を防ぐには、塩素系カビ除去材などを用いて電圧洗浄を行い、乾燥後、仕上げに防藻塗料を塗布しておくと良い。 |
 |
 |
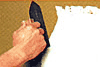 |
| 石膏ラスボード下地処理の作業 | 中塗り櫛目引きの作業 | 仕上げ鏝仕上げの作業 |
2010年5月12日
土壁塗のテクスチュア
自然の色彩と肌合いが味わい深く調和し、伝統美を表現できる
| 土壁塗は我が国在来の工法で、長きにわたる左官技能工の経験と知恵の積み重ねで培われてきたもの。材料はほとんどが天然産で、もともと各地で入手しやすい材料が使われてきたことから、地方によってさまざまな仕上げがある。現在の土壁工法は、主に京都に伝わる技法を中心としており「聚楽土仕上げ」「大津壁仕上げ」などがその代表と言える。 |
| 本聚楽水捏ね仕上げ |
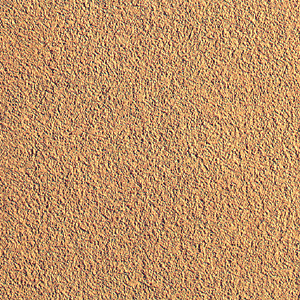 |
| 歩掛 2m2/人日 特徴 聚楽土に砂・スサを加えて水でこねた主材料を鏝で押さえて仕上げる。独特のきめ細かで品のある表情が美しい |
| 京土中塗仕上げ | 白大津仕上げ | 赤大津磨き仕上げ | ||
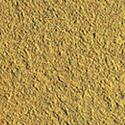 |
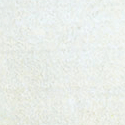 |
 |
||
| 歩掛 4m2 /人日 特徴 中塗土の持つ素朴で豊かな素材感を表現する伝統の仕上げ。藁スサの選択によって表情は多彩に変化する。 |
歩掛 3.3m2 /人日 特徴 伝統的な「押さえ壁」の仕上げで、かつては一般的な壁の上塗りとして用いられてきた。 |
歩掛 2m2 /人日 特徴 京壁の代表的な工法。色土という自然の素材ならではの深みのある優雅な光沢が魅力。高級仕上げの名にふさわしい。 |
| 九条土糊捏ね仕上げ | 京聚楽錆入り仕上げ | 京聚楽長スサ入り仕上げ | ||
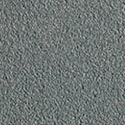 |
 |
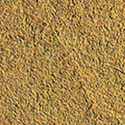 |
||
| 歩掛 3m2/人日 特徴 飽きのこないネズミ色が魅力の九条土を用いた代表的な仕上げ。川砂とふのりを混練りした材料を使用する。 |
歩掛 3.3m2/人日 特徴 聚楽土に鋼の粉を混入し、水でこねた材料を用いる。施行後、鋼の粉が湿気を吸って錆が表面に現れる。 |
歩掛 2.5m2/人日 特徴 10~15cmぐらいに切った藁スサを塗り込んだ仕上げ。素朴で温もりのある豊かな肌合いがある。 |
|
健康やリサイクルに適した環境共生型の天然素材 |
| ■特色 |
| 日本固有の風土や生活様式の中で培われた工法。壁土の種類や調合・工程の選択の自由度も高く、天然素材の色を活かした建築が得られる。防火・防水・防音性などのほか、素材自体が持つ呼吸性から調湿機能にも優れている。無公害で長持ちするうえ、味わい深く経年変化していく。近年になって、健康やリサイクルに適した環境共生型の素材として再評価され始めた。 |
| ■適した部位 |
| 住宅・一般建築の内外壁をはじめ、塀や天井など適用範囲は幅広い。 |
| ■性能評価 |
| 空気中の水蒸気を取り込むのにちょうど良い大きさの孔が多数開いているため、調湿・調温機能に優れている。また耐火性や断熱性も高い。 |
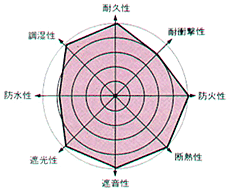 |
| ■施工工程 |
| 荒壁塗り付け後は通風を良くし、塗り面を十分に乾燥させるようにする。乾燥後のムラ直しや中塗り工程には中塗土を使用。中塗り工程では荒壁土ほど厚塗りしないため、乾燥が速い。塗り重ねが上層に進んでいくにしたがって、塗り厚は薄くなるのが一般的。なお梅雨期の上塗り施工はなるべく避ける。また寒期の施工は凍害に注意し、できれば養生する。 |
|
|
| ■下地 |
| 伝統的なものとして、木舞壁下地がある。木舞は全国的に画一的な工法はないが、縦竹および横竹それぞれの間隔は均等にとり、目透かしは割り竹の幅の約2倍以上とするのが一般的。横竹の元末を1本ごとに交互にして、木舞が平均の強度を保つようにかき付ける。このほかにも適用できる下地の範囲は広く、木摺、レンガ、メタルラス、ALCパネル、石膏ラスボード、コンクリート系下地も使用される。 |
| ■材料と調合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
荒壁土は藁スサを加え、7日以上水合わせ期間をとる。その際、古土の混入率を多くすれば一般に強度が高くなり、乾燥による収縮も少なくなる。中塗土は荒壁土と同質のものを用い、これに古い藁などを切りほぐして蒸したものを混ぜ、水練りして使用する。土の粘性、作業性は、川砂・スサを混入して調整する。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■仕上げ |
| 【土もの仕上げ】「水捏ね」「糊差し」「糊捏ね」の各仕上げは、塗り付け後、十分ムラを取り、鋼製の鏝で仕上げる。 【普通大津仕上げ】下塗りは上塗りと同じ日に行う。下塗りの際はよくムラを取り、適度に水で湿らせるが、その際表面の目をつぶし、鏝で押さえておく。 【大津磨き】上塗り後、鏝でよく磨いて、艶が出始めた頃合いに少量の水を含ませた布で塗面をふき、さらに磨きをかける。この工程を数回繰り返し、最後ビロード・フランネルなどで壁面を横一方向にふいてアクを取り、仕上げる。 【砂壁仕上げ】中塗りをよく乾燥させてから、仕上げ材料を塗り籠め、鏝押さえを十分に行い、入念に仕上げる。 |
| ■メンテナンス |
| 変形の恐れのある壁貫・木摺板などは使用せず、下塗り層は上塗り層より強くするという原則を守り、乾燥のための養生期間を十分に取る。 |
 |
 |
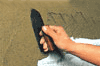 |
| 木舞かきの作業 | 貫き伏せ作業 | 中塗りの施工 |
2010年5月11日
楽水園(福岡県福岡市)
風雅な茶室を備えた日本庭園に
博多の町復興の象徴、博多塀を再現

博多 塀
土は粘性の強い黄土、瓦は旧下澤家などの古瓦、
石は焼け石に似た湯布院産の火山石を使用
2010年5月10日
社台ファームゲストハウス(北海道千歳市)
南欧のイメージと伝統の左官技術が融合
温もりに満ちたもてなしの空間

玄関側外観
玄関扉の周りに鏝押さえされた幅広の輪郭がアクセントに。
2010年5月9日
遠野浄化センター(岩手県遠野市)
「民話の故郷」の街並みに調和した
遠野瓦のナマコ壁をもつ蔵風建築

屋外機械室
見事なナマコ(海鼠、なまこ)壁で、土蔵そのものに見える。
浄の字の漆喰彫刻も気が利いている。
2010年5月8日
仙寿庵(群馬県水上市)
日本初といわれる墨流しの土壁をはじめ
特殊技法を駆使したこだわりの宿

曲面廊下
自然土壁に木鏝や刷毛で流麗な模様を描き、
部分的には鉄錆のチップ入れて赤錆を浮き出させている。
2010年5月7日
愛媛県庁本館(愛媛県松山市)
60余年ぶりの外壁全面改修によって
天然石と見紛う洗い出し仕上げを再生

正面玄関
御影石張りの車寄せ
2010年5月6日
岸邸(北海道札幌市)
ハウスメーカーとの共同作業で本格的な聚楽壁の茶室と和室を完成

茶室周り
蹲や飛び石の置かれた中庭まで室内に設けた、本格的な茶室。
聚楽壁ならではの質感が魅力的である。
2010年5月5日
養浩館(福井県福井市)
名園の池端に風雅な佇まいを見せる
福井藩主松平家の別邸を精緻に復元

主家外観
池の東畔に建つ、柿葺寄棟の数寄屋造建築。外壁は趣のある聚楽壁。
庭園に融和した風情ある姿を見せる